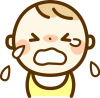お熱が出たら
通常の発熱は(41℃を越えるような高体温以外)生体防御反応の一つですから、39℃以下の発熱はむやみに体温を下げない方が良いです。熱は敵ではありません!
細菌やウイルスなどの病原体は平熱が最も活動しやすく、体温が上がるとじっとしています。また、病原体と戦う白血球は、平熱ではおとなしくしていますが、体温が上がると活発に働いて病原体をやっつけてくれます。つまり、感染症のときに熱が上がるのは、病原体を動かないようにじっとさせて、病原体と戦う白血球の活動性を高めるために身体がわざとしている、とても合理的な反応です。なので、熱があっても機嫌や食欲が保たれていれば、その熱は本人に悪さをしていないので心配いりません。むしろ、熱を利用して病原体をやっつけましょう。
しかし、熱があるときつがって食事や睡眠に影響があるときは、熱冷まし(解熱剤)を使って熱が下がっている間に食事や水分、睡眠をしっかり取らせてあげてください。熱冷ましの正式名称は鎮痛解熱剤です。なので、熱がなくても頭やのどを痛がるときは痛み止めとして使ってあげて、痛みが軽くなっている間に水分や食事、睡眠を取らせてください。
- 水分を取らせるようにしましょう。小児科医にとって一番こわいのは脱水です。本当にひどい脱水になると点滴をしようとしても血管に血液が流れなくなっているため点滴が取れなくなります。脱水の目安はおしっこの間隔を見てください。おしっこの間隔が12時間以上あくときはひどい脱水になっている可能性が高いのですぐに受診してください。少しずつでも水分がとれていて、おしっこもちょこちょこ出ていて活気があるようなら脱水はあっても軽いです。
- こどもの状態をみるために重要なのは、熱が何度あるかよりも機嫌と食欲です。熱がどんなに高くも、機嫌や食欲が保たれていればその熱は本人に悪さをしていないので大丈夫です。しかし、熱が37℃前後しかないのにぐったりして元気がない、食欲がない、おしっこが半日以上出ていない、などがあれば、その方がよっぽど重症なのですぐに受信してください。
小さい児になればなるほど、機嫌と食欲が大切です。こどもはきつくなると突然飲んだり食べたりしなくなります。なので熱があるときや食欲がないときは本人のペースに合わせるのではなく、ある程度時間を決めて定期的に水分をこまめにとらせるようにしてください。
また、水やお茶だけだと水分しか入らなくなるので、小さい児はすぐに低血糖になって動けなくなります。なので食欲がないときはイオン飲料や甘いジュースを飲ませて水分だけでなく糖分の補充もしてあげてください。 - 発熱があり、元気だったのに突然けいれんがおこり、意識障害が起これば熱性けいれんの可能性があります。熱性けいれんは脳がおかしくなったり、後遺症を起こしたりすることはありません。(ごく一部のこどもはてんかんになることがあります。)
- 少し顔を横に向けて前の首の部分(のど)を伸ばし、呼吸に障害がないようにして下さい。口腔内にタオルやわりばしをつっこむのは決してしないで下さい。もし吐いたりしたら、すみやかに吐物を手でかきだして下さい。だいたい5分以内におさまりますが、それ以上続けば救急車を呼んで下さい。半身だけのけいれんや発作後麻痺が残れば救急車を呼んで下さい。
- 座薬は39℃以上で使用するようにして下さい。
夜間不機嫌の場合は38.5℃以上で使ってもよいです。2回目は6時間以上あけて使用して下さい。1日3~4個まで。 - あかちゃんの初めての発熱は突発性発疹症という病気のことがあります。3日から5日発熱が続いて解熱、発疹が身体から顔面まででるウイルス感染症です。発疹がでれば一応安心です。
感染性胃腸炎(乳幼児嘔吐下痢症)
<原因、症状>
- 冬:
- ロタウイルス、ノロウイルスやアデノウイルスなど。
突然吐き始め、続いて水のような下痢(レモン色~白色-ロタウイルス)になります。
腹痛や熱が出ることもあります。- 夏:
- サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、腸管出血性病原性大腸菌(O-157)など。
一般に発熱、下痢に加え腹痛が強く、時に血便もみられます。原因によらず、症状が強いと脱水症がみられます。
尿量が減り、口唇が乾き、口の中の唾液の溜まりが少なくなります。
泣いても涙が出ない、目がおちくぼんでいる、皮膚が冷たく白っぽく、色が悪い、緑色の嘔吐がある、ウトウトして元気がなく、水分摂取や食欲も減退してきます。輸液が必要です。
家庭での治療 脱水の予防が大切です。
- まず吐き気止めの座薬を使って下さい。
- 吐き気が強い間は(3~4時間)薬局で売っているOS-1をスポイドかスプーンで少しずつ飲ませてください。OS-1を指定された量与えて下さい。母乳、ミルクを飲んでいるお子様は少しずつ何度も与えて下さい。無理に経口補水液に変更する必要はありません。
- 4時間以降は下痢、嘔吐のたびに乳児はOS-1を60~120ml 幼児、学童は120~240ml飲ませて下さい。
乳児:体重1kg当たり30~50ml/日(10kgの赤ちゃんの場合1日に300ml~500ml)
幼児:300~600ml/日 学童~成人:500~1000ml/日がだいたいの目安です。 - 栄養
4時間以降は年齢に合った通常の食事を再開して下さい。
母乳、ミルク哺乳中のお子様はそのまま好きなだけ飲ませて下さい。- 入浴は、嘔吐、下痢がひどい時は控えましょう。乳児はおむつかぶれがひどくなるので、排便のたびお尻を洗ってあげましょう。
- 病院から帰った後、何度も吐き続ける時は再度来院して下さい。
嘔吐物・便の処理
- ゴム手袋(使い捨て手袋)とマスク着用し、キッチンペーパーと消毒用アルコール(エタノール)と使い捨て用パック(またはビニール袋)を持って処理してください。
ノロウイルスならばミルトン液10~20倍希釈(次亜塩素酸ナトリウム)または水2Lにハイター8ml(次亜塩素酸ナトリウム)で消毒してください。
ノロウイルスはアルコール消毒は効果ありません。
衣類、ふとんなど漂白作用がありますので15分消毒後水で洗浄してください。 - 体が汚れていたら、服を脱がせて石けんで洗ってください。
- 汚れた服は脱がせてビニール袋へ入れて密閉し、衣類は80℃、10分以上の熱水処理をしてください。
- 床、椅子などは消毒してください。
- 処理に使ったペーパーなどは密閉して廃棄してください。
- ふとんやじゅうたんなどは屋外で、日光によく当てて乾燥させ、スチームアイロンやふとん乾燥機を使うと効果的です。
そのままにしておきますと乾燥してウイルスが舞い上がり、感染します。 - 手洗い、うがいをこまめにしてください。ノロウイルスは大人にも感染します。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は乾燥した皮膚に起こる病変で、アレルギーが関与していることが多い病気です。毛穴が開いていない乳幼児の肌はもともと乾燥しています。カサカサしたかゆみの強い湿疹です。赤くなり、ジュクジュクすることもあります。
皮膚は全体に乾燥していて光沢がありません。かゆみのために不機嫌になり、落ち着きがなくなることもあります。
湿疹の部位は赤ちゃんのアトピー性皮膚炎は、顔や頭に見られることが多いようです。特に頭の湿疹では厚い痂皮が付着していることがしばしばあります。幼児期になりますと、首や肘、膝の裏側に多くみられます。学童では湿疹の範囲はさらに拡大します。アトピー性皮膚炎の病態はかなり解明されてきましたがまだ十分とはいえません。
アレルギーを起こしやすい体質と皮膚が弱いという体質を両方持った人がかかるのがアトピー性皮膚炎です。
アレルギー炎症とドライスキンの2つのメカニズムがあって発症するということです。この2つの成因を治療することによって治療はある程度可能となります。
アトピー性皮膚炎は遺伝的素因に環境的要因が加わって発症し、結果的に慢性に湿疹を繰り返す疾患です。遺伝的素因はダニや家のほこり、花粉などの環境アレルゲンや卵、ミルク、大豆、小麦、米などの食物アレルゲンなどを引き金として多彩なアレルギー炎症反応が惹起されるようです。角層(角質層)がバリア機能を発揮できるのは、細胞がきっちり並んでいるだけでなく、細胞内や細胞間がケラチンやセラミドなどの繊維やタンパク質、脂質で満たされているからです。ドライスキンはセラミドを中心とした皮膚保湿機構の破綻により、乾燥肌となり、その結果、皮膚のバリア機能が障害されて皮膚過敏性とも呼ぶべきいわば敏感肌となるものです(セラミドは皮膚の角質層の中にあってうるおいやバリア機能の鍵となる。アトピー性皮膚炎はセラミドが減少している)。敏感肌になりますと、かゆくなり、掻くとバリアが破壊されます。するとますます乾燥し、悪循環が起こります。)ささいな物理化学的な刺激に過敏となりますので、手あれ、舌なめずり皮膚炎、ズック靴皮膚炎、耳切れなどが起こってきます。また微生物の経皮侵入も容易になります。また他の発症因子や悪化因子として発汗、また衣類、毛髪、化粧品、掻破などの物理的刺激、細菌や真菌の感染、接触抗原(外用薬、化粧品、金属、シャンプー、石鹸、消毒薬など)、ストレスなどがあげられます。
アトピー性皮膚炎を改善するポイントは薬で炎症を抑えた後、そこで治療終了でなく、スキンケアがバリ機能を正常に保つことです。1に清潔2に保湿、皮膚をいたわることです。
検査として血清総IgE値の上昇、血中好酸球増多、アレルゲン特異的IgE抗体検査陽性や皮膚テスト陽性があります。
人の皮膚は表皮、真皮、と皮下組織の3層より構成されています。 外界からの侵襲に対して生体内部を保護しています。ウイルスや細菌・真菌などからの感染防御、太陽エネルギー・紫外線、摩擦や接触、科学物質などの侵入の防止など、バリアー機能としての役割があります。また体内の水分や血漿・栄養分の体外への漏出を防ぐ、そして外観、容貌を形成し、他人とのコミュニケートする文化的、社会的な大きな側面を担っています。
乳児の皮膚の特徴は、皮膚(角層・表皮・真皮)の厚さは新生児期約1.2mmから成人期の約2.1mmへ成熟していきます。表皮層の厚みは11~15歳頃が最も厚いとされています。
乳児の角層の水分保持能力は低く、角層内の水分量が成人よりも少ない。そのため、冬期には、空気の乾燥により乾燥型皮膚炎の発症が増えます。
6歳ぐらいまでは毛穴が十分に開いていないため乳幼児の肌はもともと乾燥しています。皮膚を優しくいたわること。そのためには、皮膚への悪い刺激を避け、いつもきれいにして乾燥を防ぎ、潤いを持った状態に保つことが大切です。 よだれ よごれ 汗などに注意してください。
入浴
毎日お風呂にはいって、皮膚を清潔に保つようにしましょう。
皮膚の汚れおよび湿疹部位の鱗屑、痂皮はかゆみを増強し、また皮膚炎を悪化させます。
温まりすぎるとかゆみを誘発するので通常より低めの温度がよいでしょう。
皮膚は弱酸性であり、角層の機能正常に働かせるには皮膚の酸性度は重要です。
石けんの短所 石けんはアルカリ性であるという欠点があります。皮膚は弱酸性であり、角層の機能を正常に働かせるには、皮膚の酸性度は重要です。したがって頭髪には頭髪用を、皮膚には皮膚用の弱酸性のシャンプー(弱酸性の石けん)が良いでしょう。
しかしこれらの弱酸性のシャンプーや石けんは洗浄力が弱いため、長期間使用していると皮膚によごれがたまり、かゆみがでてきます。ときどき普通の石けんを使用してよごれを除去する必要があります。アトピー用の石けんでも時に接触皮膚炎を起こすことがありますので、注意して使って下さい。
皮膚を洗うときは1歳未満の乳児は手で洗うのが良いでしょう。その後は柔らかい材質のタオルやスポンジが良いと思います。泡を立て、泡でやさしくすみずみまでよく洗いましょう。
皮脂をとりすぎないよう注意してください。強い機械的な刺激は炎症を悪化させるので、合成繊維の洗い布や堅いタオルでゴシゴシこすることはやめましょう。
お風呂からあがった後は、やわらかいタオルですみずみまでよく拭いてください。
入浴直後の皮膚乾燥の対策
湿疹部位(朝、入浴直後に塗布して下さい)
ステロイド外用剤は炎症を取るには一番効果的です。過去に間違った使われ方をしたため、御両親の不安が高いようですが、湿疹がひどい場合には是非必要な薬です。ステロイド剤には弱~強の程度があり、また保湿剤を混ぜさらに程度を弱めることも出来ます。湿疹の程度や体の部位によりステロイド剤の含有量を決めます。塗る期間をしっかり守れば副作用は心配いりません。湿疹によるかゆみは睡眠障害や就寝中の掻破行動(かきむしる)を引き起こし、顔面をかいたら白内障や網膜剥離の心配も高まります。
湿疹部位には、程度によりまずステロイド外用剤(微弱~強)を使用して経過を観察します。改善すれば、程度により保湿剤単独、保湿剤とステロイド外用剤の混合剤に切り替えます。
ステロイド外用剤の使用に関しては、家族または本人と相談の上、使用していきます。
乾燥性皮膚 保湿剤を薄く朝、入浴後に全身に塗布します。
白色ワセリンが最良ですが、べたつきがあります。
白色ワセリンとザーネ軟膏の同量混合はべたつきが短く、経皮吸収良好で効果的です。
皮膚のざらざらにヒルドイドソフトも有用です。
ケラチナミンコーワ軟膏(尿素20%)は皮膚が傷つくとしみます。
また他にウレパール(尿素10%)やアズノール軟膏などがあります。
保湿剤も時に長期間の使用で接触皮膚炎を惹き起こすことがあります。
乾燥性皮膚が発赤し痒みが強くなってくる場合には、保湿剤の接触皮膚炎を疑います。
入浴剤も接触性皮膚炎を起こすことがあります。
強いかゆみを伴う乾燥性皮膚
湿疹性変化の病理像をしめすので、ステロイド外用剤をしばらく塗布します。
かゆみがほぼ消失した段階で、保湿剤や保湿剤とステロイド外用剤または非ステロイド外用剤に切り替えます。
魚鱗癬合併例 高度の乾燥性皮膚
入浴後に全身的に使用する必要があります。最も有用な保湿剤は白色ワセリンです。
ヒルドイドソフトを併用することもあります。
頭髪のケア
できるだけ毎日シャンプーで洗髪したほうがよいです。洗った後はよくすすいで、タオルでよくふいてください。 ドライヤーを使う場合は温度を低く弱めに使用してください。
シャンプーも低刺激性のものがあります。
日焼け止めの使い方
普段の使い方
晴れた日の午前~午後2時に戸外へ出るときに使います。
低刺激性(ベビー用など)のSPF20以下のものを選ぶ方がよいです。
衣服から出ている皮膚にあまり薄くなく、普通に塗ります。
2時間毎に塗りかえるようにしてください。
普段使用している外用剤はその上から塗ります。
プール、海、山、では汗や水に強い、ウオータープルーフのものを使うとよいです。
衣類
肌触りがよくて、チクチク、ザラザラしない木綿の下着、シーツ、フトンカバーが推奨されています。通気性、吸湿性にも優れているからです。
肌着は上着からの刺激を直接受けますからランニングよりTシャツ型が良いです。
洗濯後の残留洗剤は皮膚を刺激しますので、よくすすぎましょう。糊づけはよくないようです。羊毛繊維や化学繊維、かたい繊維は控え、毛布には毛布のチクチクが直接肌に触れないようにカバーをかけましょう。
掻破防止
かゆみのために皮膚をひっかくと炎症や感染を引き起こし、さらに症状を悪化させます。 爪をよくつみましょう。場合によってはソフトネットなどによる手袋やかゆみ止めの内服が必要です。湿疹によるかゆみは睡眠障害や就寝中の掻破行動(かきむしる)を引き起こし、顔面をかいたら白内障や網膜剥離の心配も高まります。早めに治療をしましょう。
オネショのあとは清潔に
オネショしたにもかかわらず、朝には乾いているという理由で、そのまま下着を着させて外出するのはよくありません。朝起きたときにシャワーを浴びさせるか、おしりだけ洗って、清潔にしてください。
運動後もスキンケアを忘れずに
スポーツの後は必ずシャワーなどでサッパリさせてください。プール、海水浴もさしつかえありませんが、シャワー後は必ず皮膚乾燥の予防のため保湿クリームを使ってしっとりさせることがケアのポイントです。
消毒
四肢の屈曲部など湿潤(じゅくじゅく)したところなどに細菌が高率に検出されることがわかりました。それが皮膚の改善を妨げている理由のひとつです。一日2~3回石けん洗浄、イソジン消毒5分乾燥後洗浄を(場合により軟膏)を繰り返すだけでかなりよくなるケースもあります。湿潤(じゅくじゅく)がひどければ早めに受診してください。とびひになっています。
ダニやハウスダストに注意
室内はていねいに掃除し清潔に保って下さい。カーペットはダニが繁殖しやすいので、できればフローリングまたは畳が良いでしょう。ふとんはよく日光にあて、十分たたいてから取り込みましょう。丸洗いも効果的です。部屋は閉め切らず、風通しをよくしましょう。
ぬいぐるみの人形はあまり持たせないようにしましょう。
カーテンは2ヶ月に1回は洗濯しましょう。
じゅうたん、畳、ふとんの上で暴れるのは禁忌です。
夜は安眠第一
かゆみでなかなかぐっすり眠ることができません。特に入浴後、温かい体のままですぐに布団に入ることは子どもには迷惑なことです。また寝苦しい夏の間はクーラーを活用してください。
内服薬
アトピー性皮膚炎の治療の目的は、アレルギー炎症の抑制、乾燥性の皮膚の改善、痒みの抑制などが考えられます。内服療法はアレルギー炎症の抑制、痒みの抑制のため外用療法の補助として使用されます。抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などがよく使われます。
ミルクアレルギー用のミルクも市販されています。(医師に相談して使用して下さい)
| 森永乳業製品 | *MA-mi(エムエー・ミー) 高度の酵素消化により、未消化の蛋白質と比べて、100万分の1程度まで低減されています。抗原性を低減 卵、大豆、魚を含まない。 *ニューMA-1 |
|---|---|
| 明治乳業製品 | *ミルフィーHP ミルクアレルゲンをほとんど含まない。 ミルクアレルギー、卵・大豆アレルギー、難治性下痢症 *エレメンタルフォーミュラ ミルクアレルゲンを全く含まない。 ミルフィーHPを用いてもアレルギー症状が改善されない場合 ミルクアレルギー、卵・大豆アレルギー、難治性下痢症 |
※表をスライドしてご覧ください。↑
これは原因と考えられる食物を捜し出し、それをしばらくの間除去することよってアトピーを治癒に向かわせようとする治療法です。その前にスキンケア、ダニ対策としての環境整備などをきちんとしておきます。
- *
- 一般にアトピーの20~30%は明らかに食物が関与しており、一方乳児で80%くらいではないだろうかといわれています。
しかしそれらの乳児がみな原因食物に対して強い反応を引き起こして強いアトピーとなるわけでなく、したがって厳格な食事制限を必要としません。この治療法は皮疹の強い難治な例に適応となるのです。 - *
- 著効・有効を含めた有効率は、乳児~成人全体で80%、乳児ほど高く95%に効果があるといわれます。
- *
- これはまず、現在の食生活上、原因として確率の高い3大食物(卵、牛乳、大豆)の混入している2次食品、加工食品を完全除去します。原因の食物であれば2~3週間で皮疹が改善してきます。その後大豆、牛乳、卵の順に経口的に摂取して皮疹の再現があれば、それを原因の食品とします。また2~3週間で皮疹の改善がなければ、米、小麦の除去を追加し、そこで皮膚症状の改善が得られたら、米、小麦、大豆、牛乳、卵の順で経口摂取を行って原因の食物を特定します。その後ある期間その原因食物制限・除去食を続けるという方法です。
- *
- 除去食の期間は早い例で3ヶ月~1年、場合によっては2、3年で耐性を獲得、摂食してもだいじょうぶとなりますので、それまでの期間ということになります。その後も少しずつゆっくりと通常の食事に戻して行く方法をとる方が良いようです。
伝染性膿痂疹(とびひ)
表皮にすり傷や虫刺され、湿疹があり、掻きむしったりすると、そこに化膿巣を生じたものです。
水疱性膿痂疹は黄色ブドウ球菌による場合が多いです。夏季に多く、乳幼児に多発します。つぎつぎに「飛び火」してどんどん広がっていくことからこう呼ばれています。全身どこにでもできますが、顔面特に鼻とその周辺、躯幹、四肢の順に多くみられます。小紅斑、水疱、さらにびらんを形成します。
痂皮性膿痂疹はA群β溶血性連鎖球菌によることが多く、小紅斑から膿疱をつくり、厚い黄褐色の痂皮を伴います。顔面、ついで四肢に多く出てきます。季節的にはいつでもできます。
治療
- 環境の改善 室温25℃以下(クーラー使用した方が良い)に保つ
- 抗生物質の内服
- 局所療法
消毒や組織の修復。
かきむしることで病変を周囲に拡大させるのでガーゼで保護します。
保育園・幼稚園
- 患部をガーゼで完全に覆ってから登園して下さい。
- 範囲が広い場合はお休みして下さい。
入浴
- 入浴はぬるめのおふろに入り、後シャワーで身体を冷やしてあがると、かゆみが少なくてすみます。かきむしるのが良くないです。
ひどい場合、プールは禁止です。
予防
- 手洗い、シャワーで皮膚を清潔に保って下さい。
- 湿疹、すり傷、虫さされのある子どもは早めに治療をして下さい。
子どもの肥満
1.肥満とは何でしょうか
肥満とは、からだの脂肪が異常に増加した状態をいいます。子どもの肥満を放置しますと高率に大人の肥満になっていきます。大人の肥満は生活習慣病の原因となります。すでに病気になってしまっている子どもも少なくありません。このため、肥満は合併症のある無しにかかわらず何らかの対応が必要です。
肥満の評価方法
- 肥満度(標準体重に対する過体重度)
肥満度(%)=100×(現在の体重-標準体重)/標準体重
20~30% 軽度肥満
30~50% 中等度肥満
50%以上 高度肥満(小児科受診が必要)
- BMI
BMI=体重(kg)/身長(m)2
成人では25ないし30が基準とされる
2.子どもの肥満がなぜ問題なのでしょうか
全国的に小児の肥満が増加していて、学齢期小児では10人に1人が肥満。
小児肥満も成人肥満同様、さまざまな健康障害をもたらすことがわかっています。
小児肥満にみられる合併症
| 系統 | 疾患・症状 |
|---|---|
| 心血管系統 | 高血圧、高コレステロール血症 など |
| 皮膚系統 | 黒色表皮症、股ずれ、皮膚線条 など |
| 内分泌系統 | 高インスリン血症、Ⅱ型糖尿病、月経早期化 |
| 消化器系統 | 胆嚢疾患(とくに胆石)、脂肪肝 |
| 筋肉骨系統 | 大腿骨頭すべり症、運動能力の低下 など |
| 呼吸器系統 | 睡眠時無呼吸症候群、肺機能障害 など |
| 精神神経系統 | 友人関係の不和などの精神的ストレス |
※表をスライドしてご覧ください。↑
3.子どもの肥満はなぜおこるのでしょうか
- 遺伝的素質
- 環境的要因
運動不足
・便利な生活で歩くことが少なくなった。
・都市化減少で遊ぶ場所が減った。
・習い事や塾のため屋外で遊ぶ時間が減少。
・パソコン、テレビゲームなど室内遊びの時間が増えた。
・交通手段の発達で歩くことが少ない。
学校生活
・食事時間が短いため、早食いになる。
・休み時間も太った子どもは外遊びをしない。 - 夜型生活習慣の低年齢化
・ 睡眠不足による日中の活動低下。
・ 遅寝遅起きによる夜食の習慣の定着と朝食の欠食。 - 食生活の変化
・ 清涼飲料水、スナック菓子、ファーストフードなどの食べすぎ。
・ 野菜嫌いで肉類への偏食。
・ インスタント食品が増えた。
・ 外食が多くなった。
・ 深夜でも食物がコンビニや自動販売機で手に入りやすい。 - 精神的な要因
・ 学校関係のストレス。友人関係や学業不振、転校など。
・ 家庭内の諸問題。
家族内の不和
共働きの増加でスキンシップの減少
少ない子どもに十分過ぎるほど食べさせる。
4.肥満の予防と治療
子どもの肥満治療の3原則は ①食事療法 ②運動療法 ③生活療法 からなっています。
子どもは大人と違って成長発達が大切なので、過度の減量は発育を阻害する恐れがありますので、ただ単に食事療法、運動療法を実施するだけに終わらずに、肥満を生じさせた問題点を明らかにする必要があります。
肥満の子どもの特徴として、内向的、非活動的で集団への参加度が低い子どもが多く、また、容姿や運動能力に劣等感を持っている子どもの存在も考えなければなりません。
食事の制限でなく、不適切な食習慣を是正しましょう。
摂食行動や体重などを自己モニターする習慣を身につけましょう。
劣等感を刺激するのではなく、うまくいった点を目に見える形でほめましょう。
① 食事療法のすすめ方
食習慣
- おやつは一日一回。朝、昼、夕の三度の食事は規則正しくとりましょう。
朝ご飯ぬきやまとめ食いは体脂肪を増やします。 - 寝る前の食事はやめましょう(夜9時以降は”食べない、飲まない”)。
使わないエネルギーは体脂肪に変身します。 - ゆっくりよく噛んで食べましょう。早食いは食べ過ぎのもとになります。
- 好き嫌いやむら食いや偏食は栄養のバランスが悪くなります。主食、主菜、副菜を毎食一人分盛りつけて食べましょう。
- テレビを見ながらの食事はやめましょう。
食事内容
- コレステロールが増えすぎないように肉と魚を同じ程度に食べましょう。
- 野菜や海草をとる工夫をしましょう。
- インスタント食品やスナック菓子は塩分の摂りすぎになりますので注意しましょう。
- 薄味に慣れましょう(濃い味付けはごはんをつい多く食べてしまう)。
- カレー、豚カツ、ハンバーグなどは高エネルギーで肥満のもとです。
- ジュース類、清涼飲料水はやめましょう。
お茶(緑茶、紅茶、ウーロン茶、麦茶など)がよいでしょう。
② 運動療法のすすめ方
運動療法の効果
- カロリーの消費
- 筋肉量増大による基礎代謝の増加
- 脂肪を使いやすいからだづくり
- 善玉コレステロールの増加
- 体力の維持、増大
- 生活習慣の改善
- カロリーの消費
摂取したカロリーより消費したカロリーが少ないと肥ります。
運動は消費カロリーを増やします。 - 筋肉増大による基礎代謝の増加
エネルギーの半分以上は、筋肉で燃やされます。したがって、筋肉量が増加すれば、エネルギー消費も増大し、肥りにくくなります。 - 脂肪を使いやすいからだづくり
脂肪細胞に蓄えられないように、運動しましょう。 - 善玉コレステロールの増加
善玉コレステロールは、動脈硬化を引き起こす悪玉コレステロールを血管壁から運び去る作用があります。運動はこの善玉コレステロールを増やします。 - 体力の維持・増大
運動により筋力の増強と心肺機能の増大が図れます。また体力がアップすることで、自分に自信が持てるようになります。 - 生活習慣の改善
運動を生活の中に取り入れることで、生活のリズムができます。お手伝いも広い意味での運動と考え、積極的に参加させてください。
テレビやテレビゲーム、ビデオの時間は1日2時間までにしてください。
エレベーター、エスカレーターをできるだけ避けて、階段を利用してください。
身の回りのことや家事の手伝いをし、ゴロゴロしないようにしてください。
学校の休み時間には、外でからだを動かす遊びをしましょう。
参考資料: 小児の肥満症マニュアル(日本肥満学会)・こどもの肥満治療テキスト(国立療養所西別府病院)
子どもの事故
1~4歳の子どもの死亡原因の第1位は不慮の事故です。 子どもの事故は、もし死亡するようなことになれば、お母さん、お父さんをはじめとして家庭全体が悲惨な状態になります。子どもは危険予測能力がなく、とてつもない発想で思いがけない行動をとります。
1.誤飲
 子どもはまさに怪獣で、ネジ、がびょう、体温計、カミソリまで食べてしまいます。
子どもはまさに怪獣で、ネジ、がびょう、体温計、カミソリまで食べてしまいます。
5歳未満の子どもで最も多いのはタバコ、次いで医薬品、化粧品、殺虫剤、洗剤などです。タバコはジュースの缶や灰皿に液体が入っている誤飲事故は重症化します。注意しましょう。
灯油の誤飲は吐かせないようにしましょう。肺炎や肺水腫の原因になります。
家族の内服薬を放置しないようにしましょう。薬箱など簡単に開けられるものに入れておくのも危険です。また殺虫剤をペットボトルに入れて流し台の下などに保管していると誤飲事故のもとになります。
10円玉など丸い物を飲み込んだ場合食道にあれば尿カテーテルで除去可能です。
ボタン電池は同一部位に長時間停留すると穿孔を発生する可能性がありますので、磁石付きカテーテルで取り出します。
2.窒息
 食べ物の誤飲ではアメ玉やゼリー、ナッツ類、みかん、ぶどう、ウインナー、おもち、硬貨などで窒息例があります。口の中に食べ物がある間は、おしゃべり、ふざけ、遊びなど止めましょう。風船をくわえて遊んでいるうちに、のどにつまって窒息することがあります。紙やビニールにも注意しましょう。またブラインドを巻き上げるヒモなども首に引っかかって窒息の原因になります。赤ちゃんのふわふわ布団は危険です。赤ちゃんの周囲にはザブトンや枕なども置かないようにしましょう。
食べ物の誤飲ではアメ玉やゼリー、ナッツ類、みかん、ぶどう、ウインナー、おもち、硬貨などで窒息例があります。口の中に食べ物がある間は、おしゃべり、ふざけ、遊びなど止めましょう。風船をくわえて遊んでいるうちに、のどにつまって窒息することがあります。紙やビニールにも注意しましょう。またブラインドを巻き上げるヒモなども首に引っかかって窒息の原因になります。赤ちゃんのふわふわ布団は危険です。赤ちゃんの周囲にはザブトンや枕なども置かないようにしましょう。
応急処置:小児の場合は、膝の上にうつ伏せにしたり、腰を抱えて肩胛骨の間を手のひらで5回ぐらい強めにたたきます。乳児の場合は、指を口の中に入れて舌を押さえて、少し柔らかくたたきます。心臓の拍動がなく、チアノーゼ(体が紫色になる)がでたら、心マッサージを開始してください。
3.熱傷
 熱傷が発生したら、まず受傷時に熱が深達するのを防止するとともに鎮痛効果もありますので衣服の上から水道水で冷却しましょう。熱傷部位の範囲が広範な場合の冷却は子どもの場合、低体温、ショックを起こすことがあり注意して下さい。
熱傷が発生したら、まず受傷時に熱が深達するのを防止するとともに鎮痛効果もありますので衣服の上から水道水で冷却しましょう。熱傷部位の範囲が広範な場合の冷却は子どもの場合、低体温、ショックを起こすことがあり注意して下さい。
炊飯器や湯沸かしポットの水蒸気の出口を手で触る熱傷がよく見られます。
子どもが触れない場所に置きましょう。ガスレンジにも気を付けましょう。
つかまり立ちの年齢の子どもが、テーブルクロスを引っ張ってその上のラーメンや熱いスープ類を浴び、熱傷を起こすことがあります。テーブルクロスは止めましょう。
薄い風呂のふたの上に乗って遊んでいて、浴槽に転落して熱傷をおこしたりする事故もあります。浴室には鍵をかけましょう。
夏の浴衣での花火は、浴衣に燃え移ることがあります。花火には注意しましょう。
家を留守にする時は、マッチ、ライターをチェックして、手の届かないところへ置きましょう。いたずらで火事になることもあります。
4.事故
 転落、転倒事故は非常に多く発生しています。ハイハイし始めから十分に気を付けて下さい。軽症の頭部打撲は冷やして下さい。特に6時間以内に不機嫌、嘔吐、顔面蒼白などの症状が認められた場合、頭蓋内に血腫ができていることがあります。緊急処置が必要です。
転落、転倒事故は非常に多く発生しています。ハイハイし始めから十分に気を付けて下さい。軽症の頭部打撲は冷やして下さい。特に6時間以内に不機嫌、嘔吐、顔面蒼白などの症状が認められた場合、頭蓋内に血腫ができていることがあります。緊急処置が必要です。
乳児を「高い、高い」したり、揺すったりすると、頭頸部がつよく揺すられ、頭蓋内出血や眼底出血を引き起こすことがあります(ゆさぶられっこ症候群)。また子どもの腕を強く引っ張ると肘内障(ちゅうないしょう)といって、肘(ひじ)の靱帯がずれる恐れがあります。腕を痛がって、ほとんど動かさなくなります。
家庭内、家庭外にふつうにあるものが、突然凶器に変身します。注意は必要ですが、子どもの冒険心をそぐのはよくありません。
交通事故は特に注意が必要です。社会ルールは繰り返し子どもへ伝えましょう。
5.溺水
 子どもは水遊びが大好きです。水槽などをのぞき込んだとき、頭が大きくバランスをくずして落ちやすいので注意しましょう。
子どもは水遊びが大好きです。水槽などをのぞき込んだとき、頭が大きくバランスをくずして落ちやすいので注意しましょう。
入浴時は子どもから目を離さないよう、入浴後は浴槽の湯を抜いておきましょう。また浴槽のふたは丈夫な物にして、浴室には鍵をかけましょう。
洗濯機の水は洗濯が終わったら水を抜きましょう。バケツや洗面器に水を張らないようにしましょう。トイレにも注意してください。
プールでは子どもから目を離さないでください。
日頃から近くの池や小川に近づかないよう話してください。
赤ちゃんの便秘
基本的に赤ちゃんが機嫌よく、母乳をよく飲んで、体重増加も順調であれば心配ありません。
排便は個人差があり、1歳過ぎまで便秘が続くことはよくあります。
新生時期は栄養の吸収が活発なのですが、腸の粘膜の機能は未発達なので、どうしても腸液や胆汁なども多く、便の回数も多くなります。しかし、生後 数ヶ月経ちますと、腸の粘膜の吸収力もだんだんしっかりしてきて、逆に便の回数も減ってきます。したがってこの時期、急に便の回数が減ったと感じても、あくまで生理的なものです。
便秘で注意したいのはヒルシュスプルング病という病気です。多くの場合は生後すぐから、排便がなくおなかが腫れて元気もなくなるので、新生時期に発見されます。
生まれつき腸を動かす神経細胞に異常があるので腸が動けなくなってしまうのです。体重増加が順調でおなかが異常に腫れてなければ心配ありません。
排便がうまくいかない場合はお風呂あがりにおなかを時計方向にゆっくりマッサージしてあげましょう。薬店で販売しているマルツエキスや5%の砂糖水あるいはプルーンジュースなどの果汁がよいことがありますが、かなり個人差があります。それでも排便がない場合は綿棒にオリーブ油を浸して、おしりの穴から2cmくらい差し込んでクルクルと回して刺激してみてください。
それでもだめなら浣腸を試みても差し支えありません。よくいわれるように「くせ」になることはありませんので安心してください。
熱性けいれん
発熱があり、元気だったのに突然けいれんが起こり、意識障害が起これば、熱性けいれんの可能性があります。
乳幼児の脳は未熟なため、急激な体温の上昇に伴ってけいれんを起こすことがあります。
熱性けいれんは脳に後遺症を起こしたりすることはありません。(ごく一部の子どもにてんかんへ移行することがあります)
こども15人~20人に1人は経験するきわめてありふれた病気です。両親など家族が子どもの頃起こしたことがあれば、熱性けいれんを起こす可能性が高くなります。
1~2歳が起こしやすい年齢ですが、生後6ヶ月から6歳くらいまでは起こす可能性があります。過半数の子どもでは熱性けいれんは生涯に1回しかけいれんを起こしません。2回目を起こす頻度は25~50%(平均30%)と報告されています。
熱性けいれんは全身を突っ張った後、手足をガクガク振るわせる左右対称性の強直性間代性発作のことが多く、ほとんど5分以内でおさまります。
けいれんを起こしたからといって、すぐに生命にかかわるような危険な状態にはなりません。
発作時の家庭での応急処置
- あわてないで落ち着くこと
- 衣服をゆるめる。特に首まわりをゆるくします。
- 仰向けにして頭を横に向け、頭部をそり気味にし、のどの部分を伸ばし呼吸に障害がないようにして下さい。
- 口腔内にタオルやハシを突っ込むのは決してしないで下さい。
- もし吐いたら、すみやかに吐物を手でかきだして、口腔内、鼻孔内の吐物、分泌物を拭き取って下さい。
- 体温を測り、どのようなけいれんが何分間ぐらい続くか時計をみて確認しながらよく観察します。
- 口から薬や飲み物を与えてはいけません。
- 元に戻るまで必ずそばにいるようにして下さい。
緊急に病院を受診する必要がある場合
- 発作が10分以上続く
- 短い間隔で繰り返し発作が起こり、この間意識障害が続くとき
- 身体の一部の発作、または全身性であるが体の一部の動きが特に強い。
- 1歳未満での初回発作
- 発熱と発作に加え、他の神経症状を伴う時(意識障害が続く、麻痺など)
熱性けいれんの予防について
熱性けいれんが起こりやすいお子さまには、発熱時に抗けいれん薬を使用するのがよいでしょう。
この方法により、熱性けいれんを予防することが可能です。
熱性けいれんは、体温が急激に上昇するときに起こりやすいので、37.5°C前後の発熱に気づいた時には、できるだけ速やかにあらかじめ処方されているけいれん予防の坐薬(ダイアップ)を肛門内に挿入して下さい。
発熱が続く場合は8時間後にさらにもう1回、座薬(ダイアップ)を挿入して下さい。
2回目挿入後は、さらに発熱が続いても、それ以上坐薬(ダイアップ)を使用する必要は有りません。
- *
- けいれん予防坐薬(ダイアップ)に解熱薬坐薬(アンヒバ)を併用する場合には、30分以上間隔をあけて下さい。
- *
- 熱性けいれん後3ヶ月間は予防接種を受けることができません。
熱中症
熱中症とは、高温環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
長時間暑い環境にさらされて大量の汗をかくと水分や塩分が不足して脱水状態になり、体内の熱をうまく外に逃がせなくなってしまいます。また湿度が高い環境では、汗をかいてもその汗が蒸発しにくく、やはり体内の熱をうまく逃がせなくなります。
熱中症は、熱波により幼児が高温環境で起こるもの、若い世代では炎天下や厚さの厳しい環境での労働やスポーツ活動中に起こるものなどがあります。中高年では、屋内の日常生活で発症することもあります。症状は軽症では、四肢や腹筋などに痛みをともなったけいれん、筋肉痛、多量の発汗その後数秒間程度の失神、脈拍が早く弱い状態、呼吸回数の増加、顔色不良、めまい、唇のしびれなどがみられることがあります。運動をやめた直後に起こることが多いとされています。すぐ風通しの良い日陰かクーラーの効いている部屋へ移り、脱衣し、身体をあおぐか、氷嚢で冷やしてください(首、脇、そけいぶ)。
中等度では、めまい感、疲労感、虚脱感、頭重感(頭痛)、失神、吐き気、嘔吐などのいくつかの症状が重なり合って起こります。
重症では、意識障害、おかしな言動や行動、過呼吸、ショック症状などが起こってきます。意識があっても、水分を自力で摂取できなかったら、すぐ医療機関へ搬送してください。意識がない状態や呼びかけに対し返事がおかしい場合はすぐ救急隊を要請してください。
熱中症環境保健マニュアルより
RSウイルス
RSウイルスの特徴
乳児気道感染症(細気管支炎、肺炎など)の主な原因ウイルスです。
名前の由来は呼吸器(respiratory tract)感染症患者から分離され、感染細胞が多核巨細胞つまり合胞体(syncytium)を形成するという特徴からです。
パラミキソウイルス科に属します。AとBの血清型があり、さらに各血清型に多くの遺伝子型が知られています。エンベロープ(脂質でできた膜)をもち環境中では不安定で、石けん、消毒薬などに出会うと容易に感染力を失います。
11月~3月の冬期に流行します。特に12月がピークです。免疫性のない乳児の約半数が1回の流行で初感染すると推計されています。小児期を通じて1回の流行にあたり、10~20%の割合で再感染します。成人の再感染は症状が軽い。保育園などの暴露率の高いところでは発生率は高く、初感染では100%、再感染は60~80%です。何度も感染します。
接触や飛沫を介して気道に感染し、2~5日の潜伏期の後、発熱、鼻水、咳などで発症、通常1~2週間で軽快します。しかし2歳以下での乳幼児ではしばしば上気道炎から下気道に進展して細気管支炎、肺炎を発症し、特に6ヶ月以下の乳児では入院加療を必要とすることがめずらしくありません。免疫不全児、低出体重児や呼吸器・循環器に疾患を持つ乳幼児は重症化しやすく、特に注意が必要です。
臨床症状
初発症状は鼻汁と咽頭炎です。咳は多くは1~3日後に出現し、微熱~中等度の発熱を伴います。咳の出現後まもなく喘鳴(ゼーゼー)が出てきます。進行しますと、咳と喘鳴が増悪し、呼吸困難を生じ、呼吸数の増加、肋間陥没、チアノーゼ(顔面蒼白で口唇が紫色になる)が出現してきます。こうなりますと、すぐ救急車を呼んでください。
中耳炎を併発しやすい。
迅速診断キットで調べることは可能です。(まだ保険適応なく、医院の支払い)
予防
乳児は人ごみをさけた方がよいでしょう。
マスク、手洗いをこまめにしましょう。
石けん、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウムなどにふれると容易に感染力を失います。
登園・登校
主要症状が軽快したら登校可能です。
ヒトメタニューモウイルス感染症(hMPV)
ヒトメタニューモウイルスの特徴
小児の呼吸器感染の5~10%を占める原因ウイルスです。RSウイルス感染症とよく似た症状を認めます。パラミキソウイルス科に属します。
流行期は春が一般的ですが、時に他の季節にもみられます。小児から成人までの広い年齢層で感染を繰り返します。
臨床症状
症状はRSウイルスと類似しており、発熱、咳、鼻汁と咽頭炎です。潜伏期間は4~6日です。咳は多くは5日前後、微熱~中等度の発熱を伴います。咳の出現後まもなく喘鳴(ゼーゼー)が出てきます。乳幼児、高齢者、免疫不全状態の患者では、細気管支炎、気管支炎、肺炎を発症することがあります。
多くの場合は症状を抑える対症療法が主になります。軽症の場合は、水分補給、睡眠、栄養、保温、加湿をして安静にして経過をみてください。
予防
乳児は人ごみをさけた方がよいでしょう。
飛沫感染と接触感染でうつるため、マスク、手洗いをこまめにしましょう。
登園・登校
主要症状が軽快したら登校可能です。
肺炎球菌とインフルエンザ菌感染症
小児科の外来診療で最も頻度の高い気道感染症(咽頭炎と扁桃炎を除く)および関連疾患(中耳炎、副鼻腔炎など)さらに侵襲性疾患(細菌性髄膜炎、細菌性骨髄炎、インフルエンザ菌での喉頭蓋炎)の主たる病因菌は肺炎球菌とインフルエンザ菌の2菌種です。
海外の多くの国では、1990年代初期からインフルエンザb菌(以下ヒブと記載)
ワクチンの導入によりインフルエンザ菌による侵襲性疾患はすでにありません。また米国では7価肺炎球菌結合型ワクチンの2000年以降の導入により肺炎球菌の侵襲性疾患は激減しています。
<病因菌としての頻度>
気道感染症
肺炎における喀痰培養:インフルエンザ菌が50%程度、肺炎球菌が30%程度、モラキセラ・カタラーリスが10%程度
急性中耳炎の鼓室穿刺液培養:肺炎球菌が40%程度、インフルエンザ菌が25%程度、モラキセラ・カタラーリスが15%程度
肺炎球菌
グラム陽性の球菌であり、3~4歳までは十分な抗体の上昇はみられません。
ほとんどの小児の鼻咽腔の常在菌であり、特に2歳前後、集団保育、冬期における分離率は高い。常在菌として数ヶ月は定着しますが、これだけで十分な感染防御のための免疫を獲得することはできません。
インフルエンザ菌
ヒトはインフルエンザ菌の唯一の自然宿主です。肺炎球菌と同様に、ほとんどの小児の鼻咽腔の常在菌です。
グラム陰性の多形成の桿菌です。莢膜をもつ菌種はa~f6種で、最も侵性が強いのはb菌である。b菌の検出頻度は少なく5%以下ですが、血管内に侵入しやすく、さらに血管内でのクリアランス機構に対する抵抗性が強い、このためインフルエンザ菌による細菌性髄膜炎を含む侵襲性疾患の病因菌の95% 以上を占めます。
参考文献:開業医の外来小児科学
細菌性髄膜炎
小児の細菌性髄膜炎は、5~10%が死亡し、30~60%に後遺症を残す予後不良な疾患です。半数以上が1歳前に発症します。
細菌性髄膜炎の主な起炎菌はインフルエンザ菌b型(以下、ヒブ)と肺炎球菌です。ヒブ髄膜炎の増加に伴い、細菌性髄膜炎が全体として増加傾向にあります。
このため小児科外来、救急外来では注意を要しますが、発症早期の診療の場では発熱以外の症状、所見が乏しいため、早期発見が困難です。
また抗菌薬の耐性化問題で、治療も困難であるため、ワクチンの導入が望まれていました。例えばヒブワクチンが導入により、デンマークでは2005年のヒブ髄膜炎総数はわずか2例です。日本では年間発生数は500人以上と推測されています。
起炎菌の種類と頻度
細菌性髄膜炎の起炎菌を諸外国と比較すると、起炎菌の頻度に大きな違いがあります。わが国では起炎菌としてインフルエンザ菌(ほとんどはヒブ)がきわめて多く、全体の70%であり、次いで肺炎球菌、B群連鎖球菌、大腸菌(この4種類で90%)などがつづきます。リステリア、髄膜炎菌、ブドウ球菌は少数です。 年齢によって病原菌の違いがあります。
- 新生児~生後3ヶ月乳児:B群連鎖球菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌、リステリア菌
- 生後3ヶ月以降の乳児~幼児:インフルエンザ菌(ほとんどがヒブ)、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌
- 年長児~青年期:肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌
- 成人:肺炎球菌、髄膜炎菌
- 高齢者(50歳以上):肺炎球菌、グラム陰性桿菌、リステリア菌
症状
発熱、嘔吐、頭痛、けいれん、意識障害
乳児では発熱、哺乳力低下、鳴き声が弱い、不機嫌、四肢の動きが少ない
大泉門膨隆
参考文献:開業医の外来小児科学